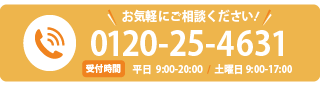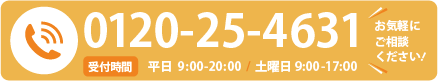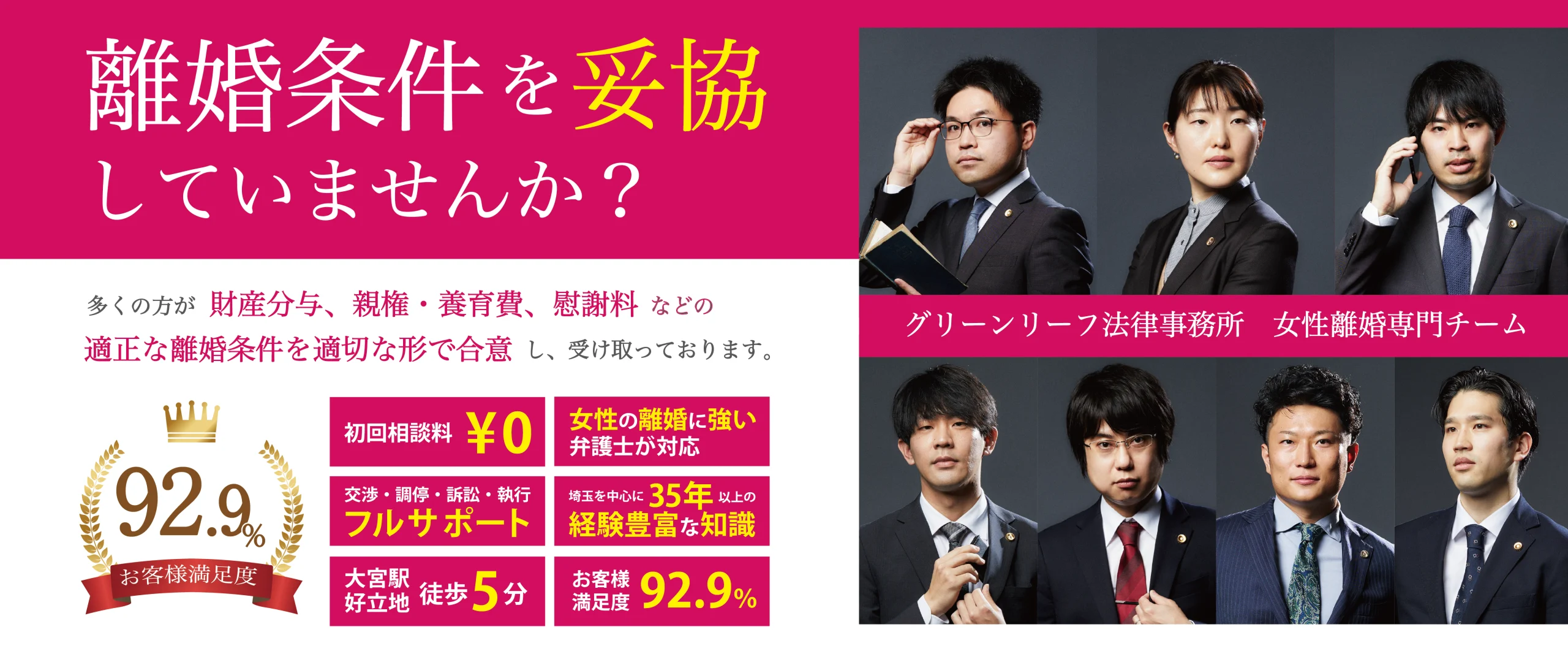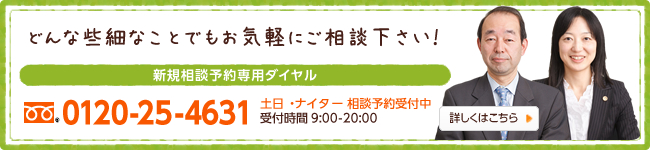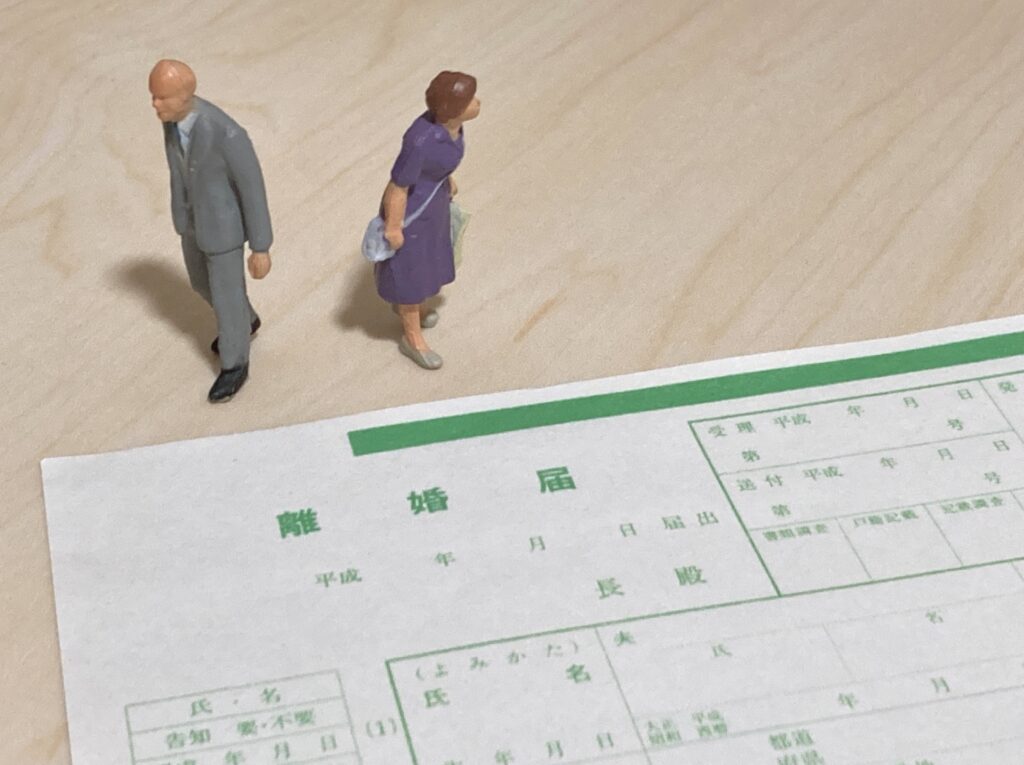
20年ほど前からドラマにも取り上げられ話題になり、世間に認識されるようになった「熟年離婚」ですが、いわゆる「熟年夫婦」が離婚するというケースはいまや決して珍しいものではありません。熟年夫婦が離婚を考えるときに、どのようなことに注意をすればよいのか、解説していきます。
熟年離婚をするときのポイント
熟年離婚とは

「熟年離婚」というのは法的な用語ではなく、明確な定義があるわけではないようですが、一般的に長年婚姻関係を結んでいた夫婦が離婚する場合を指して表現されるものです。
令和4年(2022年)度の厚生労働省による「離婚に関する統計(人口動態統計特殊報告)」によれば、離婚した夫婦の同居期間は昭和25年(1950年)以降、同居期間「20年以上」の割合が上昇傾向にあり、昭和25年には5%程度だったのが令和2年(2020年)には21.5%にまで上昇しているようです。
すなわち、今や離婚する夫婦の5組に1組は、熟年離婚であるといえるのです。
熟年離婚とそうでない離婚との違い

通常の離婚において決めるべき事項としては、
・離婚するか否か
・(未成年の子がいる場合)親権者となる者の決定
・(未成熟子がいる場合)養育費
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
が挙げられることが多いと思われます。
熟年離婚の場合、子は既に独立している場合が多く、親権者や養育費を定める必要があるケースはほとんどないと考えられるのに対し、長年の婚姻生活により夫婦共有財産として築いた財産は大きいことが多いため財産分与が問題になるケースが多いように思われます。
また、離婚原因については夫婦によってそれぞれ異なるでしょうが、離婚原因となる有責行為により精神的苦痛を被ったという場合、熟年夫婦であればその精神的苦痛も大きく、したがって慰謝料も高額になる、という可能性が考えられます。
さらに年金分割は、婚姻期間により分割する対象期間が決まります。国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、夫婦双方の合意がなくても分割することができる制度(いわゆる3号分割)がありますが、熟年離婚の場合は平成20年3月までの婚姻期間が一定程度あると考えられるため、この3号分割ではなく合意分割により年金分割を定めるべき、というケースも多いでしょう。
以下、熟年離婚の場合に考慮すべき財産分与・慰謝料・年金分割について少し詳しく見ていきましょう。
財産分与について

財産分与とは、夫婦が離婚したときに、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算するため分与をすることをいいます。
その趣旨は、夫婦が婚姻中に築いた共有財産を清算分配すると共に、離婚後の配偶者の生活の維持に資することにあるとされています。これを受けて、財産分与の内容には「清算的要素」及び「扶養的要素」があります。
ただ、単に「財産分与」といった場合には、このうちの「清算的要素」を指していることがほとんどですので、このコラムの中ではこの要素の意味での財産分与について扱うことにします。
熟年離婚の場合の財産分与の重要性について
財産分与の対象は、婚姻中に築いた共有財産ですから、熟年離婚の場合、その対象も幅広く、量も多い、ということが多いでしょう。
「婚姻中に築いた共有財産」が対象なので、基準の終期は「夫婦の財産形成に向けた協力関係が失われた日」、一般的には別居した日が終期とされることが多いと思われます。
婚姻前、つまり独身時代に既に有していた財産については「特有財産」といって、原則的には財産分与の対象になりませんが、特有財産と共有財産が混在している形になっている場合は、もはや分与の対象の区別がつかない、として特有財産を別に考えることができないケースもあります(以前のコラム「財産分与における特有財産について~婚姻前の預貯金~」参照)。
熟年離婚の場合、独身時代の貯蓄(特有財産)がもはやいくらあったのか分からなくなっているケースなども多くあります。特に預貯金等は、通帳の紛失・取引履歴が古すぎて開示できない、といった可能性もあります。上記のとおり、婚姻後に共有財産と一体化してしまうケースもあり、その場合裁判所としては「特有財産としてはもはや特定ができない」として混然一体となった預金残高を全て共有財産として分与対象とすることもありますので、その点は「どこが特有財産といえるのか」という判別がつくように資料を準備しておかねばならず、注意が必要です。
慰謝料について

離婚時の慰謝料の発生原因としては、一般的に「不貞」や「DV」といったことが有責行為として挙げられることが多いと思われますので、このような行為を理由に慰謝料請求するケースで考えてみましょう。
慰謝料の相場って?
不貞慰謝料の請求方法としては、裁判に限らず、交渉や調停によって合意して支払いを約束してもらうこともあります。
交渉や調停の場合、相手方が真意に基づいて支払義務を認めれば特にいくらを慰謝料として請求しなければならない、というものでもありません。
しかし、裁判の場合は、裁判官が当該不貞の有無を判断し、その内容を考慮して、慰謝料をいくらと決めることになります。裁判に関しては、慰謝料の認容額の傾向というものがあり、おおよそ100万円から300万円の範囲で認めているのではないかと考えられ、平均値としては150万円程度であるといわれています。
慰謝料の増減に影響する要素
慰謝料について、「このような要素で判断せよ」と法律などで定められているわけではありませんが、一般的には①婚姻期間、②支払側の資力、③有責性、④未成年の子の有無等があげられることが多いと考えられます。
実際に①の婚姻期間がどの程度慰謝料額に影響を与えられているのかは不明ですが、統計としては婚姻年数が5年未満の場合は慰謝料(裁判手続の中で決まった支払い合意のできた解決金)として平均額167万円、5~10年未満の場合は同197万円、10~20年未満は同240万円、20年以上の場合は同413万円となっており、婚姻年数が長くなれば金額も増加されるのではないか、という指摘があります。
ただ、これは裁判で争った際に、「解決金」として「慰謝料」として以外の要素を考慮して判断していること、つまり財産分与等の要素を含めて金銭の支払い合意をしている可能性もあることから、必ずしも慰謝料額が増えているだけではないかもしれないという点に注意が必要です。
上記の要素①婚姻期間だけではなく、②支払い側の資力、という観点でいえば、婚姻期間が長い、すなわち配偶者も高齢になっており収入も高くなっている、ということが考えられます。
さらに、例えば不貞期間やDVの被害が遭った期間も熟年離婚の場合は長くなることがあり得、③有責性、すなわち精神的苦痛をもたらした悪質さがより評価されて、慰謝料がより高額になる、ということが考えられます。
年金分割について

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金や共済年金部分を分けることです。
年金分割の対象
財産分与と同じように、配偶者の厚生年金・共済年金の納付実績を原則、婚姻期間中の分につき2分の1ずつ分けるということが可能になります。
注意点としては、配偶者が自営業者等で、国民年金しか納めていない場合は年金分割できません。
特に収入を得ておらず、貯蓄や退職金もない長年主婦・主夫をやってきたという方にとってすれば、自身に収入がないからこそ、配偶者から年金分割をしてもらい、老後の年金をもらうということが非常に重要だといえるのです。
年金分割は、「しなければならない」というものではないので、配偶者と年金分割について決めずに離婚をしている夫婦もいるかもしれませんが、まだ離婚をした日の翌日から起算して2年を経過していない場合は、必ず手続をするようにしましょう。
既に述べているとおり、熟年離婚の場合は合意が要らない3号分割ではなく合意分割の方が分割の対象期間が長くできるため、もし「年金分割はしっかりしたいが、配偶者が合意に応じてくれない」という場合は、調停などの家庭裁判所における法的手続を検討されるのがよろしいかと思います。
家庭裁判所では、「3号分割ではたとえ別居期間があっても分割割合を0.5としていることとの均衡」や、「夫婦双方の老後の保障という年金制度の趣旨」から、原則として分割割合を0.5とする判断がされています。ですから、配偶者が離婚には応じるものの、「年金分割の分割割合に納得してくれない」とか、「そもそも年金分割の合意をしてくれない」という場合は、家庭裁判所の判断に委ねることにも合理性があると考えられるのです。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。