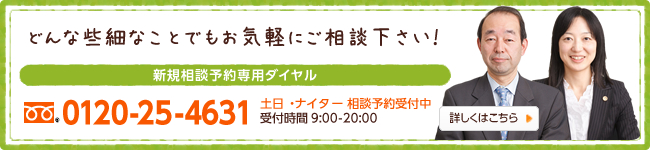新しい民法が令和8年(2026年)4月1日から施行されます。これまでの民法では父母以外の親族と子の交流については法律上定めがなく、たとえば祖父母らと子との親子交流(面会交流)は祖父母らに審判申立権限がないとされてきました。しかし改正民法では一定条件の下、祖父母のような第三者にも交流を認めるという規定があります。そこで今回は、新しい民法下で明文化された新しい親子交流について、認められる条件等を、説明したいと思います。
新民法下での親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)とは
令和8年(2026年)4月1日施行前の民法での交流の考え方

面会交流とは,非親権者・非監護親(子どもと暮らしていない親)が,子どもと会ったり,手紙や電話等で交流したりすることです。令和8年施行の民法(以下「改正民法」といい、従前の民法を「現行民法」といいます。)では、これまで面会交流と言われていた親子間の交流のことを「親子交流」と呼ぶようになりましたが、中身としては変わるものではありません。
親子交流は、子どもの権利と考えられ、子どもの成長及び人格形成に必要といわれていることから、基本的には子のために実施するのが良いと考えられています。
もちろん、例外はあり、虐待や,子ども自身が拒否していること,その他面会交流ができない事情があれば、子どもにとって望ましくない以上、親子交流を認めるべきでないというケースもあります。
親子交流の方法

親子交流の実施方法は様々なものがあり、
- 実際に会う親子交流(第三者が付き添うこともある)
- 間接的な親子交流(電話、手紙、メール、写真、など)
があります。法律上はどのような方法で実施せよということを規定しているわけではありませんから、協議離婚や調停離婚で定める場合などは、この実施方法まで具体的に決めることもあります。
現行民法と改正民法での親子交流の違い
父母以外の親族との交流

現行民法では、父母以外の親族(祖父母等)と子の交流に関する明文規定がなく、最高裁で令和3年に出された決定でも、「父母以外の第三者は、事実上子を監護してきたものであっても、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることができないと解するのが相当である」と判断していました。
すなわち、仮に祖父母が子を父や母の代わりに育ててきたとしても、その後別居するに至った後、子と交流するために裁判所に判断をしてもらうということはできなかったのです。
このような令和3年の最高裁の決定は、要するに父母以外の第三者は、どのような範囲でどのように交流を求められるのかということを立法に委ねるものでした。改正民法では、新たに一定条件の下、父母以外の第三者にも交流を認める場合があることを規定したため、祖父母らにも子との交流について申立ができるようになりました。
父母以外の者に交流を認める条件

改正民法は、766条の2の第1項で、「家庭裁判所は、子と父母以外の親族との間に親子関係に準じた親密な関係が形成されているなど、子の利益のために特に必要があると認めるときは、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる」としています。
申立権者の範囲

上記条文からも明らかなとおり、仮に子と親しい関係にあったとしても、父母以外の誰でも彼でも申立ができるわけではなく、一定の親族関係にある者に申立権は絞られています。
具体的には、この直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、「過去に当該子を監護していた者に限る」とされており(改正民法766条の2の2項2号)、さらに子との交流の申立てができるのは、原則として子の父母(同項1号)、他に適当な方法がないとき(父母の一方が死亡した場合など)は、父母以外の子の親族から申立てをすることができる、としています。
申立てが適法になるためには、その者と子との交流について定めをするため他に適当な方法がないときに限るとされ、いわゆる「補充性」が必要となります。
これに加えて、「過去に当該子を監護していた者に限る」と監護実績の要件もあり、「子の利益のために特に必要がある」という実体的要件があって初めて父母以外の親族と子の交流を認めるという構造です。
過去の「監護実績」とは

では、どの程度の監護があれば、この交流を認めるべき要件があるといえるのでしょうか。
これはあくまでも評価になりますが、そもそも子との交流は、父母との親子交流と同様、既に形成された愛着関係を離婚(別居)後も維持することにその目的と正当性が認められるので、小野監護というのも父母と同様に考えられるほど明確な監護実績が必要といえます。
すなわち、当該親族と子が生活の本拠を共にしていたなど、こと当該親族との間に愛着関係が形成される素地があった場合、ということになります。また時間としても、単に同居していた時期があるというにとどまらず、客観的に愛着関係を形成できる程度の期間にわたる程度の期間が必要でしょう。
愛着関係、ということに注目するならば、一定の期間生活の本拠を共にし、愛着関係を一度築いたと評価されるなら、その後別離状態がしばらく続いていても、その期間交流がないことをもって、監護実績があったことを否定することはできないとも考えられます。
まとめ

以上のとおり、改正民法は父母以外の親族にも別離後の子との交流を認める余地がある法律となっています。
もっとも、その申立権者は単に親族であるというだけでは充たされるものではなく、父母にも代わる愛着関係を築くことができた、監護実績のある親族に限られています。
したがって、安易に「孫に会える非親権者方の祖父母が救われる」といえるものではありませんが、子のために父母代わりだった親族が救われる余地を残した点に、令和3年の最高裁の決定が指摘した論点についての、前進が見られるといえるでしょう。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。