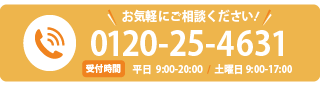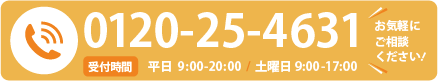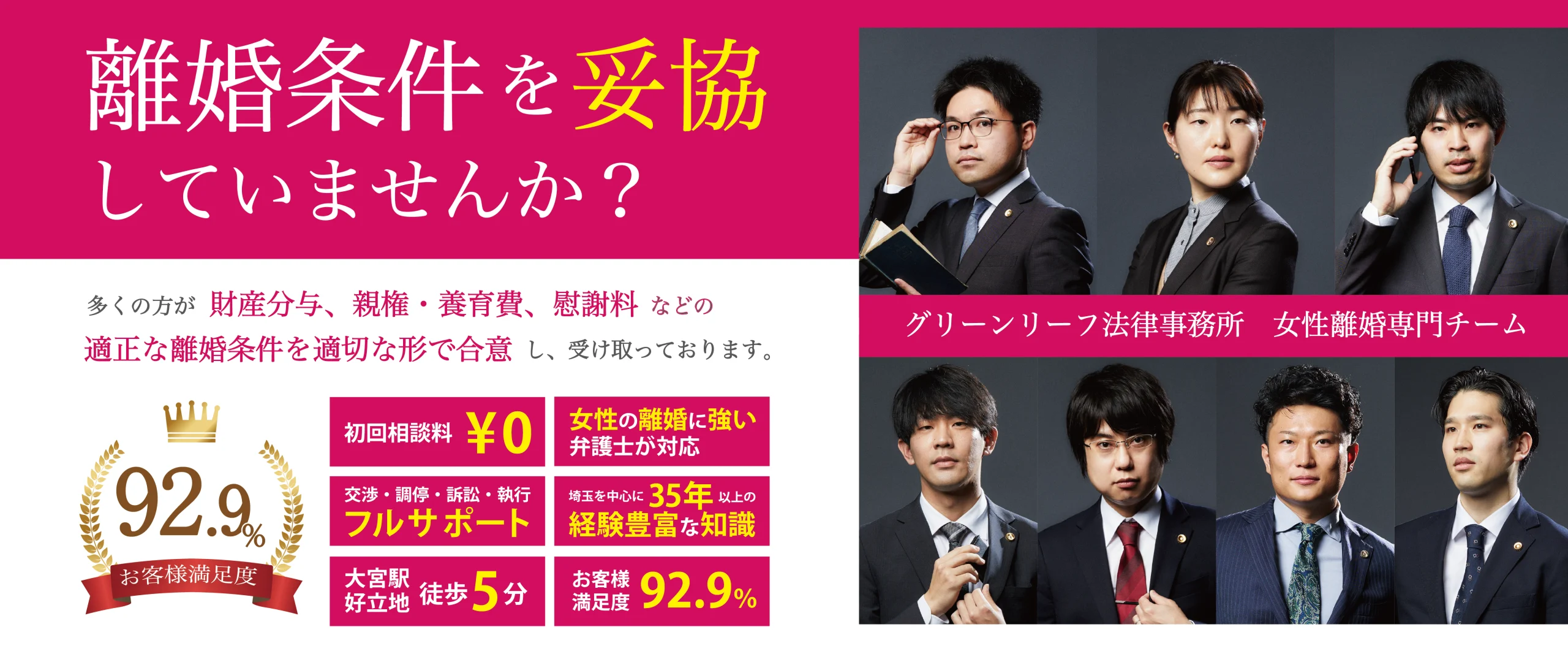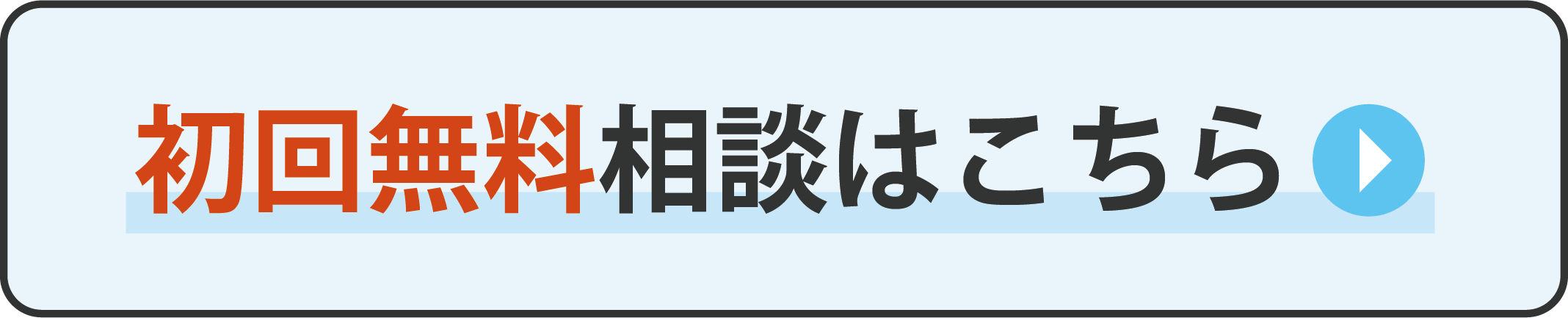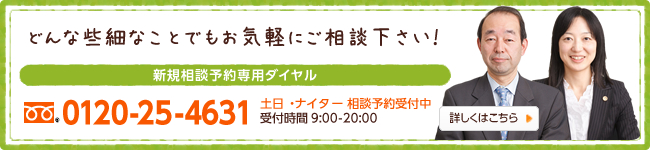紛争の内容
今回は、子らが妻側の監護下にあったところ、夫側が勝手に子らを遠方の実家に連れ去ってしまい、連絡が途絶え、子らを返してもらえないというケースでした。
夫側は、全く子らの引渡しに応じず、子らの生活状況に心配がある状況でしたので、当職らにおいて、まずは子らの引渡しに関するご依頼をいただきました。
ここで、子らの引渡しを求める手続について簡単に説明をいたしますと、まず、家庭裁判所において、監護者を妻側とすべきという判断をしてもらったうえで、子らの引渡しを求める手続きをとります。具体的には、監護者指定、及び、子らの引渡しの審判、並びに、その仮処分を申し立てることとなります(仮処分とは、簡単にいうと、審判の内容を相手方が争ったとしても、最終的な判断がなされるまで、審判の効力を維持させるものになります)。
本件でも、管轄の裁判所に対し、夫側を相手方として、子の監護者指定、及び、子の引渡し、及び、その仮処分の申し立てを行いました。
交渉・調停・訴訟等の経過
監護者指定・子の引渡しの審判手続の中では、監護者を妻と夫のいずれかにすべきかという点で、真向から主張が対立いたしました。
夫側は、これまでの妻側の育児対応に問題があったと主張していたのに対し、こちら側(妻側)は、これまで主たる監護を行っていたのは妻側であり、連れ去られた後の子らの監護状況にも不安がある点を主張いたしました。
この点、家庭裁判所の調査官が入り、どちらを監護者とすべきかについて調査が尽くされました。
調査の中では、家庭裁判所での妻・夫と子らの交流の様子を確認したり、子らの意思を確認したり、夫婦それぞれと調査官が面談を行うなどがなされました。
また、その間、当職ら代理人を通して、子らと妻との面会交流の調整を行ったり、監護者を妻とすべき点などの主張を行いました。
結果、調査官の調査報告書においては、妻を監護者と指定すべきとの判断がなされたため、夫側に任意での子らの引渡しを求め、無事、子らの引渡しを受けることができました。
その後、離婚調停のご依頼もいただき、調停の中では、夫側と子らの面会交流をどのように取り決めるかが大きな争点となりました。
本事例の結末
夫側は、遠方の実家に住んでいるため、直接の面会交流の日程などの条件について議論が難航いたしましたが、当職らが面会交流の条件について主張を尽くした結果、子らと夫との面会交流は年4回、また、面会交流の際の交通費は相手方の負担とするといった妻側にも無理のない条件で、面会交流の条項を定めることができました。
最終的には、面会交流の条件も定まったため、無事に離婚調停も成立となりました。
本事例に学ぶこと
他方の配偶者が勝手に主たる監護者の下から子を引き離し、連れ去ってしまった場合には、本件のような手続きを経ることで、子の引渡しを求めることになります。
もっとも、上記の審判や仮処分の手続きには、専門的な知識が必要となりますので、上記のような内容でお困りの際には、一度、離婚問題に精通した弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
弁護士 相川 一ゑ
弁護士 渡邉 千晃