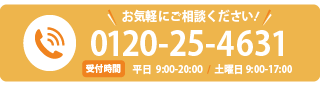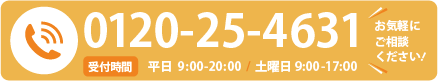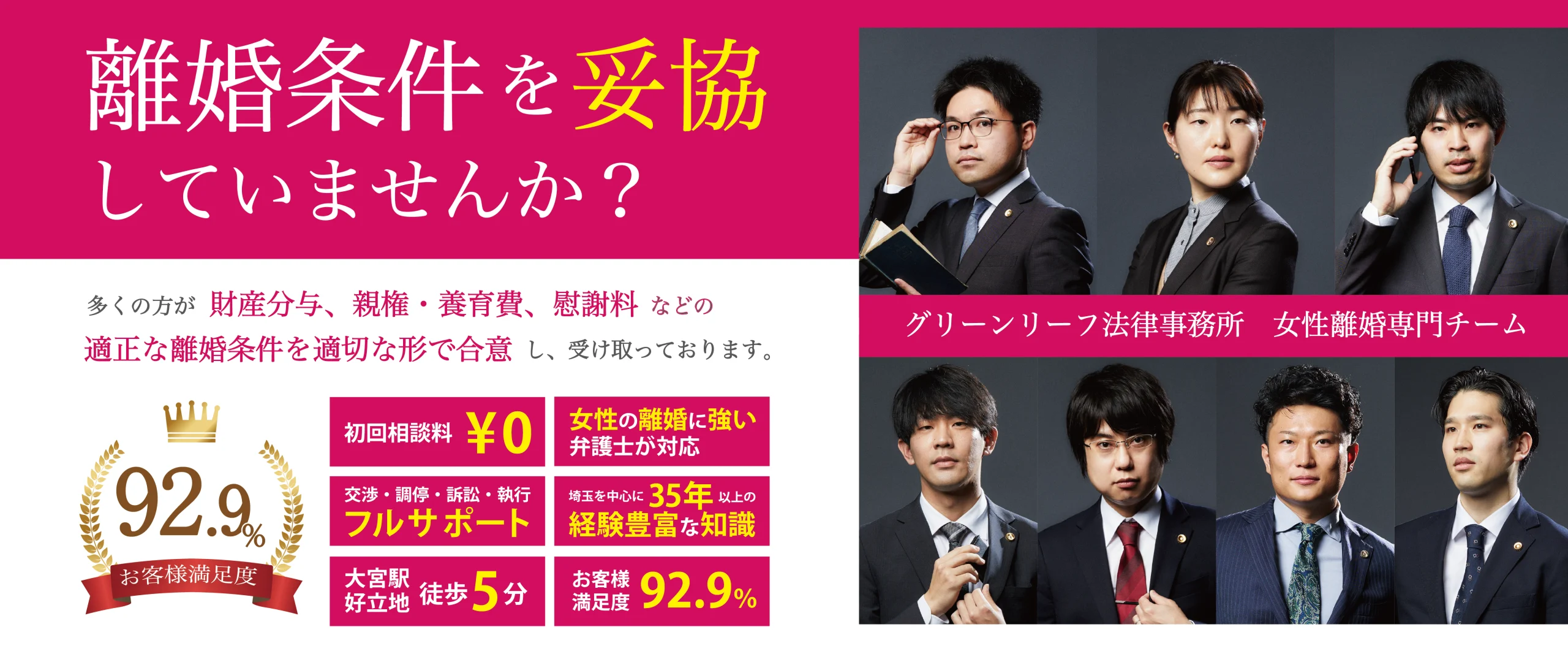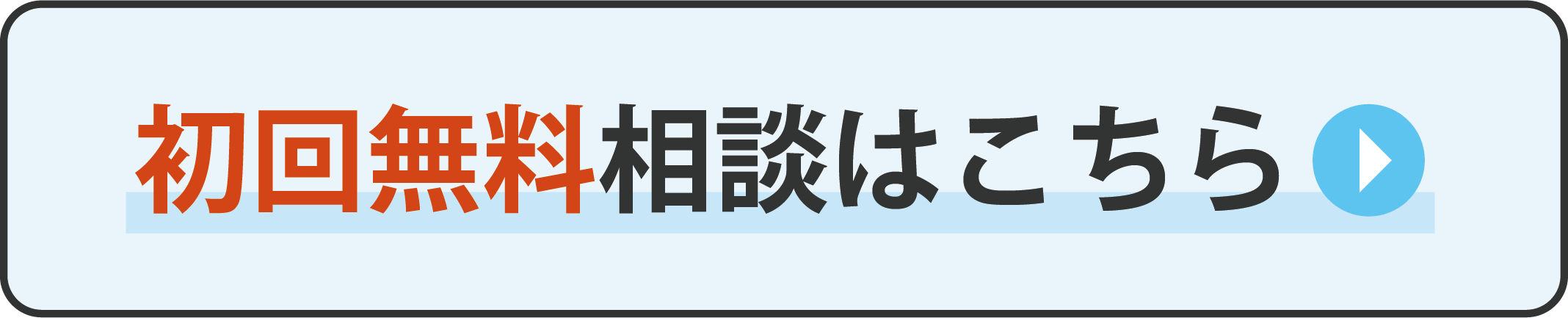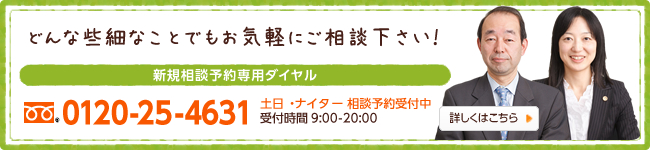紛争の内容
パートで働いていたAさんは、会社員である夫Bと折り合いが悪く、幼稚園に通う子どもCはいるものの、離婚を考えていました。
夫BもAさんとの夫婦関係を継続する気はなく、ある時離婚を前提に、県外の実家に突然引っ越してしまい、別居状態が開始しました。
子どもCもBには懐いていたため、月に1度の面会交流はしていたものの、AさんがCと住んでいた自宅はBの名義で建てたものであったため、その処理などが問題となり、AさんもBもそれぞれ弁護士を就けて、財産分与も含めて協議離婚の交渉をすることとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
AさんとBとの婚姻期間は約5年でしたが、B名義の自宅はローンも残っており、分与方法が決まらない状態でした。
Aさんは、子どもの生活をあまり変えたくないとの考えで、これまで住んできた自宅は自分名義にしたいと考えていました。
本事例の結末
Aさんはたまたま遺産を得ており、この残ローンを支払ってその代わりB名義からAさん名義にする、ということも経済的に可能な状態にありました。
そこで、不動産業者に自宅の査定を得、オーバーローンではないことを確認し、Bとも情報共有した上で、残ローン全額の負担を対価として、自宅をAさん名義とすることになりました。
それ以外には大きな財産はなかったものの、Bがこれまで受け取っていた児童手当全額をAさんに返金してもらうこととして、財産分与としました。
養育費についても定めをし、まだ支払終期迄は10年以上あるということで、念のため離婚条件を全て公正証書とすることになりました。
本事例に学ぶこと
財産分与については、裁判所の考え方では夫婦の共有財産を2分の1ずつする、というのが基本的ですが、もちろん当事者双方が納得していれば、そのような分け方に限定されるものではありません。
本件のように一部の財産のみを分与対象とすることや、分与方法を2分の1ずつとしない、ということも可能です。
このような協議ができない場合は、離婚調停をするほかありませんが、双方落としどころを探して協議離婚ができるのであればその中で合意することも可能です。
ただ、財産分与をして金銭で清算する場合や、養育費の支払いなど、金銭支払いについての合意を伴う場合には、協議離婚においてその合意を証明するため、あるいはその支払義務につき不履行があったときに強制執行可能とするため、公正証書を作成することをお勧めします。
弁護士 相川 一ゑ