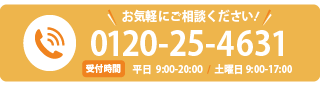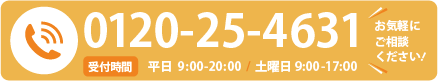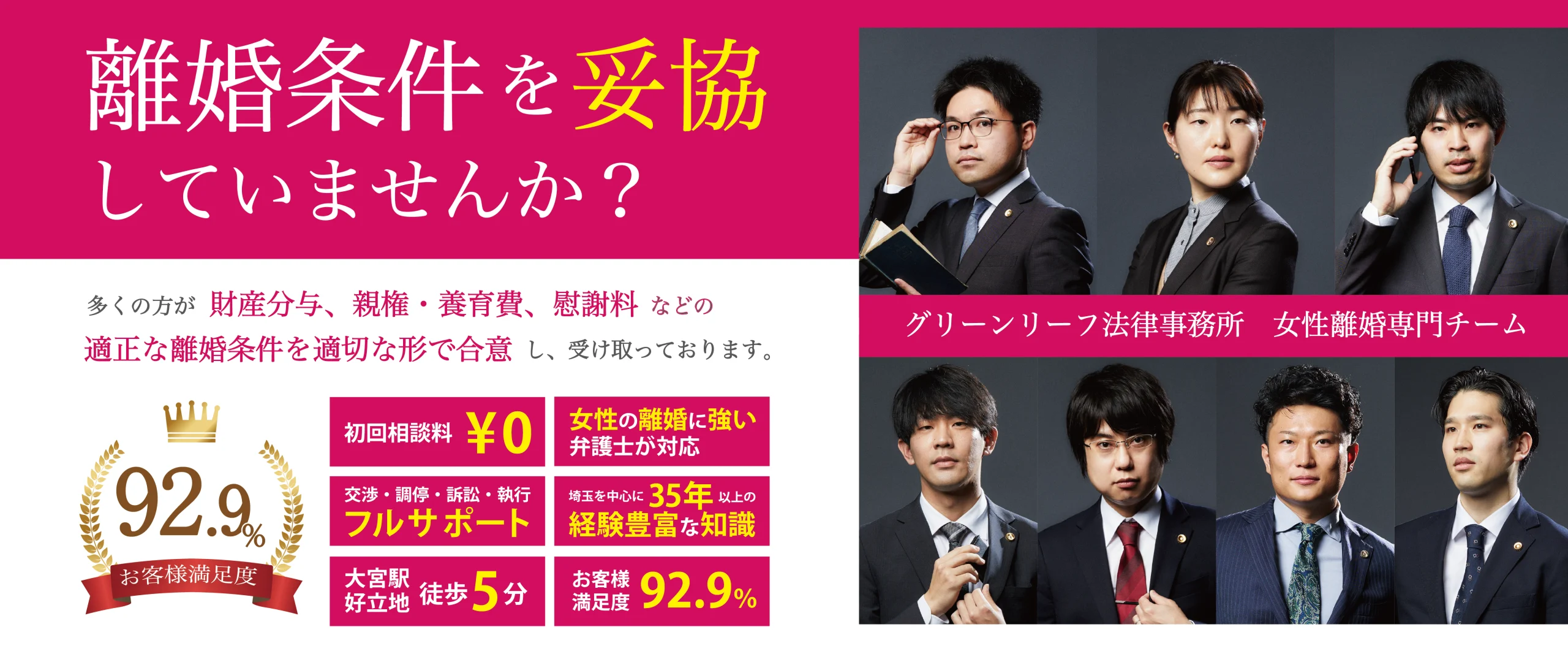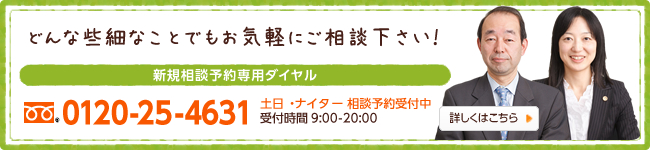紛争の内容
Aさんは、夫Bが精神的に不安定な状態が続き、長男Cも怯えるようになったため、警察にも相談の上、夫Bと同居していた県内の戸建て住宅から転居し、避難することにしました。
幸いにもAさんは大手国内メーカー会社に勤務していたため、自分だけでも生活費等を捻出することはできましたが、夫Bにも責任を果たしてもらうため、婚姻費用分担の調停を申し立て、毎月夫からの婚姻費用の支払いを受けていました。
夫Bは長男Cとの面会を求めるため面会交流の調停を申し立ててきましたが、こちらについては長男Cが同居中夫Bが目の前で奇行を繰り返すなどしていたので、父親であるBに会うことを嫌がるということを家庭裁判所の調査官の調査によっても明らかにできたため、直接的な面会交流ではなく、間接的な手紙のやり取りだけに留めることができました。
しかし、併せて夫Bが申立ててきた離婚調停については、夫Bが親権を争い、AさんとBとで共有していた県内の戸建て住宅の分与方法にも争いがあったため、調停不成立となり、訴訟にて争うことになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
離婚訴訟の中では、本件戸建て住宅が既にローンを完済していたことから、その評価などが問題となりました。
Aさんは独身時代のお金を頭金として支払っており、Bもまた親からの支援を受けてローンの大部分を返済していたからです。
本事例の結末
そこで、裁判の中ではAさんとBのそれぞれの特有財産からの貢献度を割り出し、婚姻中の同居期間に関する貢献度も考慮して、Aさんがこの戸建て住宅を単独所有とし、Bの共有持分を買い取って清算する、ということになりました。
また、親権についてはCと面会交流すら間接的にしか実施できない状況を考慮し、母であるAさんと定めることになりました。
本事例に学ぶこと
親権については、調停などでも調査を実施していれば、それが重視されることが多いです。
面会交流の実施状況なども重要となります。
また、財産分与について特有財産が関わる場合には、財産分与のこれまでの原則運用であった2分の1ルールをそのまま適用することができません。実際の支払い状況など、資料を集めることがポイントになるので、過去の資料を見つけ出すことができるかが判断の分かれ目になります。
弁護士 相川 一ゑ